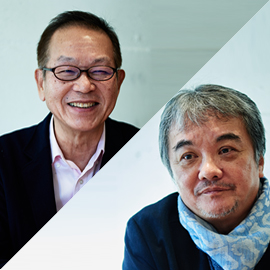シンクロナイズドスイミング(シンクロ)の日本代表選手として、アトランタ五輪、シドニー五輪、アテネ五輪の3大会に連続出場。シドニーでは団体のみならずデュエットにも出場し、見事銀メダルに輝きました。五輪3大会を通して3つの銀メダルと1つの銅メダルを獲得。世界水泳福岡大会のデュエットではシンクロ界において、日本史上初の優勝を果たし、金メダルを獲得するなど、輝かしい実績を誇るのが武田美保さん。現在は、三重県知事を務める夫・鈴木英敬氏の政治活動を支えつつ、講演活動や三重県のシンクロクラブで指導を行っています。
テレビをはじめとしたメディアへの出演で、今やお茶の間でもすっかりおなじみになった戦場カメラマン・ジャーナリストの渡部陽一さん。数多くの戦場で戦争の悲劇を見聞きし、そこで生活する人々の声を取材。お子様が生まれた今もなお、戦場に足を運び、写真を通して戦場に生きる子どもたちの声を届けています。一方で、その体験をもとに、戦場で生活している人々の家族の絆や人間が持つ愛の深さ、命の大切さ、生きることの素晴らしさなどをテーマにした講演活動を行っており、講演会では、あの独特の語り口調が実際に聴けるとあって好評を博しています。
今回はスペシャル対談として、お二人に『世界・仕事・家族』、そして講演にかける思いなどを熱く語っていただきました。
小学校のときから、オリンピックに行けると信じていた
渡部:
今は戦場カメラマンとして世界の戦場を取材していますが、僕の幼少期の夢は、魚博士になることでした。静岡県にある海の町に生まれ育ち、魚釣りばかりしていたので、そのうちに世界中の魚を見てみたいと思うようになりました。だから当時の僕は、戦場カメラマンになるなんて夢にも思いませんでしたね。
世界とのつながりもまったくありませんでした。世界とつながっていたのは、唯一テレビぐらいですね。当時、好んで見ていた番組といえば、『なるほど!ザ・ワールド』。中継の後ろに現地の人や生活の様子が映るんですが、あんなところに行ってみたいと思いました。もうひとつ、鮮烈に覚えているのが、ビールのコマーシャルに出てきた国際ジャーナリストの落合信彦さん。映像に衝撃を受け、国際ジャーナリストという肩書きに興味を持ちました。世界に興味を持ったのはこれらがきっかけだったのかもしれません。
武田:
泳げるようになりたくて通ったスイミングスクールで、たまたまシンクロをやってみないかと誘われたのが、小学校2年生のときでした。すぐにシンクロが好きになり、うまくなりたくて、夢中になりました。練習に行くのが、楽しくて仕方がなかったですね。
世界を意識したのは、小学校6年生のときです。ソウル五輪をテレビで見ていたのですが、テレビの向こうの大舞台で、小谷実可子さんが大観衆の声援を受けていました。その様子を見て、『私もオリンピックに出るんだ』と強く思いました。そして、8年後にあの舞台に立つために、今から準備をしなければならないと思ったんです。
渡部:
もうビジョンをお持ちだったんですね。
武田:
画面の向こうのオリンピックは、私にとって大変魅力的でした。そんな舞台があるのなら、目指すほかないと思ったんです。
 渡部:
渡部:
僕の転機は、大学1年生のときに受けた生物学の授業でした。アフリカのジャングルには、“今でも動物を狩猟しながら生活している狩猟民族がいる”と聞いたんです。僕は実際に行ってみたくなったし、直接会って、話を聞いてみたいと思いました。本当にいるのか、自分の目で確認したかったんです。それでアルバイトで貯めたお金で格安航空券を買い、一人でジャングルに飛び込みました。
ところが当時、その森の一帯ではルワンダ内戦が起きていました。僕は世界情勢をまったく理解していなかった。森の中で少年兵に襲撃を受け、持ち物を奪われました。そんな僕の目の前に現れたのが、血まみれになり、泣きながら「助けてください」と僕の袖を引っ張る現地の子どもたちの姿でした。何も知らなかったとはいえ、かなりの衝撃を受けました。
この事実を伝えたいと思った僕は、自分にできることは『その姿を多くの人に届けることだ』と考えました。“好きなカメラで写真を撮って、子どもたちの声を届けよう”、こうして戦場カメラマンになりました。
武田:
「憧れのオリンピックによく行けたね」と言われますが、私は『絶対にオリンピックにいける』と自分自身を信じていました。
あるデータを見てびっくりしたんですが、日本の子どもたちは世界に比べて突出して自己肯定感が低いんです。日本では謙虚な姿勢が評価されますが、謙虚というのは「私なんかできません…」と遠慮したり、卑下したりすることではなく、自分がどんなに上達しても、どんなポジションを獲得しても、それでも上に向かって努力を続けることだと思うんです。
自己肯定感が高いことの他に、自分自身をいつも客観的に分析していたことがオリンピックへつながったと思っています。練習のことを常に母に報告していたので、“何ができていて、何ができていないのか”が明確になりましたし、状況を整理して言語化できるようにもなっていました。自分の強みを生かす振り付けは何か、そんなことを考えるのも好きでしたね。自己分析をしながら、自分を成長させることを常に考えることができました。
渡部:
自己管理が徹底されていたんですね。小学校時代からなんて、頭が下がります。
武田:
好きだからこそできたんです。
渡部:
以前、別の競技のアスリートと結婚された元シンクロ選手の記事を読みました。どうやって自分の肉体を高めていくか、お互いに教え合うんですが、その元選手はそこで初めて自分の練習がいかに極限まで自分を追い込んだものだったかを知ったと。
時には水の中で意識を失ったり、水面に浮かんだり、水底に沈んでしまうほどのこともあるそうですね。記事を読んで、人はここまでできるんだと思ったことを覚えています。自らを管理し、肉体を追い込み、そして何より気力の強さを養う。ハッとさせられました。
武田:
私も他のアスリートの練習を見て思ったことがあります。「えっ!?たった2時間で練習終わりなの?」と(笑)。私たちは毎日10時間、ずっと水の中で練習していましたから。
渡部:
いや、本当に人はここまでできるのかと思ってしまいます。
 武田:
武田:
ここまで来るのには環境の影響も大きかったと思います。“そこに全力を賭けていいんだと思わせてくれる親のバックアップ”があって、“ここまでやらないといけないんだという絶対的な道標を作ってくださるコーチ”がいました。
渡部:
僕の場合は、戦場カメラマンになりたいと思ったものの、戦場カメラマンという仕事がどう成り立っているのかわかりませんでした。無鉄砲に戦場の中に飛び込み、現地で写真を撮り、日本に持ち帰ってきて、新聞社や雑誌社の扉を叩いて写真を見てもらうんですが、写真をまったく使ってもらえない日々が続きました。
おかげで、次の戦場に行く資金も、日々の生活資金も手元になくなってしまい、日雇いのアルバイトでなんとか食いつなぎました。半分を生活費にあて、残りを取材費にし、また戦場に飛び込むということを続けるうちに、世界中から来ている同業の戦場カメラマンに最前線で会うようになりました。
万が一のときに逃げるルートを確保するために情報交換をしたり、食糧を分け合ったり、帰るための車をシェアしたり…。さまざまな助け合いの中で、世界中の戦場カメラマンが駆け出しの僕に、写真のアングル、ニュースの組み立て方、各国で求められる報道写真の色合いなどを、夜のテントの中、ひたすら待ち続ける時間の合間に教えてくれました。
そこから教えられた通りに写真を撮ったり、媒体を選んだりしているうちに、徐々に写真を使ってもらえるようになりました。僕の一番の先生は、戦場で出会った世界の戦場カメラマンですね。
中学3年生のときにジュニア世界選手権に行ったんですが、そのときに日本の指導者の目線の高さを感じました。世界で勝つ、ということを指導者がものすごく意識されていたんです。
世界の選手は、大きく筋肉を伸ばして早く回転させ、ダイナミックな演技をするのですが、日本人が同じことをしても体格で負けてしまう。そこで、観ている人がここまでやるのかと驚き、感動するぐらいの精度の高い演技で勝負しようと考えていらっしゃったんです。
私は当時ジュニアチームの中で最年少でした。周りにいる外国人の選手はものすごく大きくて、大人に見えました。でも、練習を見て、『負けていない』と思いました。私が見ても、日本のレベルは高かったんです。そのとき、先生の方針は本物だと思いましたし、世界で勝つための視野を持った人に教えてもらえているんだと実感しました。
石の上にも15年。コツコツこそ最大の力になる一歩
渡部:
大学1年生のときから名乗り始めた戦場カメラマンでしたが、そこから10年は写真を使ってもらえませんでした。でも、戦場カメラマンをやめたいと思ったことは一度もありませんでした。アフリカ、中東、中南米、アジア、中央アジア…。世界の現場に行くと、目の前で世界史がダイナミックに音を立てて動いている。
歴史が動く瞬間を目の当たりにしてゾクゾクし、歴史の証人として現場に立てることこそ、カメラマン冥利に尽きると思いました。この瞬間を追い続け、記録を残していくことが仕事だと。そうすると、写真を使ってもらえなくても、それほど気にならなかった。 ただ、日雇い労働をしながら資金を作っているときにも、世界の現場からは新聞や雑誌に写真や記事は配信されているわけです。それを見ていると、クレジットに知っている名前が続々と出てくるようになった。スティーブ、フレデリック、オサマ…。みんなは現場にもう入って、写真を撮っているのかと思うと焦りました。
 武田:
武田:
シンクロ選手として困難にぶつかったといえば、21歳のときです。それまでは、ステージごとに超えないといけない相手がいたりして、勝ちたいという思いだけでトントンと進んで行くことができたんです。ところが、やがて自分自身に勝たないとここは超えられないという、自分との戦いになってきたことを認識し始めました。ここからが長い戦いでした。
ちょうど、デュエットで立花美哉さんと組むことになった頃です。デュエットでは、技術的に差があっても、それぞれの持つ雰囲気が似ていたり、体型が似ている選手を組ませることが一般的なんですが、日本の選考会は技術が1位と2位になったことを評価して2人を選びました。立花さんは、私とは真逆とも言える選手で、身長も5センチ違うし、雰囲気も違いました。私は後輩でしたから、胸を借りる立場でした。でも、立花さんにどう合せたらいいのかわからない。
私を指導してくださったコーチは、性格によって言葉のかけ方を変える方でした。私は打たれ強く、厳しくしたら発奮すると思われていて、厳しい指導が何年も続きました。立花さんに合わせるには、体格の小さい私が足を高く演技しないといけないのですが、やっても、やっても認められないんです。
初めてネガティブな気持ちになりました。でも、やっぱり私自身の問題だと気づいたんです。『逃げるわけにはいかない。自分に勝たないと前には進めない。無理だという概念を自分で取り払わないといけない』と。 やめようと思ったこともあります。でも、一瞬で打ち消されました。自分に負けて辞めるのは悔しすぎるから。一生、悔いが残ると思いました。
渡部:
賑やかな街や華やかに遊ぶ若者たちにも関心は向かいませんでしたね。“苦しんでいる世界の子どもたちに会いに行き、それを世界に伝えるのだ”という鉄の柱が身体の中にありましたから。生活そのものが、最前線の取材を柱に1年1年組み立てられている日々でした。
世界から戦争がなくなるときがきたら、戦場カメラマンという仕事ではなく、学校カメラマンとして、世界中の学校で学ぶ子どもたちが楽しく学ぶ姿を写真に残したいと思っています。
武田:
私も学校帰りに何か食べたりする高校生や大学生っぽいことをうらやましいと思うことはありませんでした。自分の中で、シンクロで活躍できているシーンを想像するだけでドキドキワクワクしていました。遊びよりも、もっと自分を満たしてくれる何かがあったんですよね。
そしてシンクロを続けるうちに、自分の中で“達成感”というものが次第に変わって行きました。最初はメダルを取って授与されるシーンを思い描いたりしていたんですが、だんだんと得点の高さやメダル獲得ではなく、自分の頭の中に描いた演技の完成形にいかに近づけたか、何パーセントできたか、という達成感にこそゾクゾクするようになりました。自分の中での独特の感覚で、ここをこうすれば、あのときああしていれば、という思いを持ちながら、日々達成感を追求していたので、毎日がとても充実していました。
よくオリンピック3大会もモチベーションが維持できましたね、と聞かれることがありますが、ずっと自分の理想を追いかけていたので、特にオリンピックのためにモチベーションを維持する必要はなかったんです。自分の中の達成感が満たされたことなんて一度もなかったから、『まだまだやらないと』という気持ちをずっと持っていました。
渡部:
改めて勝利への一番の近道が自己管理なんだと感じました。一つひとつの言葉の持っている力や実感から来る説得力が伝わってきます。僕も自己管理をしたいと常々思いますができない。
世界の戦場に飛び込んでいったのは、環境を強引に変えていくことで、自らを鼓舞していたところもあったかもしれない。
武田:
でも、シンクロでは命は取られません。戦場カメラマンは命の危険と隣り合わせです。はるかに高い自己管理力がないとできない仕事だと思います。
 渡部:
渡部:
現場の戦場カメラマンは僕にとって一番の先生でしたが、もう一人、大きく影響を受けた先生がいます。その先生がおっしゃったのが、“石の上にも15年”という言葉でした。どんな仕事でも、どんな勉強でも、どんな趣味でも、とにかくコツコツコツコツ毎日やめずに続けることこそが大事だと。それこそが、最大の力になる一歩だと。
だから、写真を使ってもらえない中でも、10年やそこらなんて、まだまだフレッシャーズだったのだと気づかされました。やがて15年経って、ありがたいことに写真を大きく使ってもらうことができるようになり、先生に報告に行くとこう言われました。“石の上にも25年”。 とにかくカメラマンとして、今できることをやる。講演会に声をかけてもらったら、講演で世界の子どもたちの声を伝えていく。新聞でも雑誌でも、コツコツコツコツやっていきなさいと。
武田:
飛び級で行きたいと思っても、やっぱり近道はないんですよね。なりたい自分になるためには、反復練習しかなかったりする。それ以外に身につく方法なんてないんです。
渡部:
先生は父親のような存在であり、指導者です。現場に一緒に立ったら、負けないよう奮い立ちます。東日本大震災のときは、一緒に被災地の最前線に入り、沿岸部をすべて回りました。先生の写真の撮り方、取材の仕方、現地の人とのふれあい方、すべてが自分の中に染みこんでいきました。
武田:
ぜひひとつ、たくさんの人に知ってほしいことがあります。それは、“アスリートは一生できない”ということです。どんなに人生を賭けたスポーツも、いつか現役を引退しないといけない。これは大変な問題なんです。スポーツ選手のセカンドキャリアの問題がささやかれていますが、丁寧に議論しないといけない。簡単な話ではないですから。
渡部:
それは僕から写真や取材が突然、奪われるということですね。もし、今自分が必死になっている世界がなくなったとしたら…。背筋が凍る話です。多くの人が、手を差し伸べないといけないですね。
家族の支えがあるから、これまでやってこられた
武田:
アスリートとして結果を残せた背景には、家族の大きな支えがありました。栄養管理から精神面まで、物心両面で本当に充実したバックアップ体制があったからこそ、私はシンクロに打ち込めました。
母はスポーツをやっていたわけではありませんでしたが、大きな影響を与えてくれました。何より、私以上にポジティブな人なんです。こんなにポジティブな人はいるのか、というくらいに。
例えば小学校のとき、コーチに厳しいことを言われて泣きながら帰ったことがありました。母に報告すると大笑いするわけです。「オリンピックに行ける選手だと見込まれているから、そこまで叱ってもらえたんだ。むしろ喜ばないといけない」と言われました。
私をわざと盛り上げてくれていたことも後に知りました。あるとき、明日は学校行事で練習に遅れます、と事務連絡で母とコーチが話をしていました。でも、その内容を知らない私は何を話していたのか気になる。すると、母は嘘を言うんです。「この練習はここまで上手になっていると言ってたよ」と。そんなことを聞くと、私の気持ちは盛り上がるわけですね。
渡部:
お母さんは武田さんのことを本当によく知っておられたんですね。
武田:
人間関係の悩みもアドバイスをもらいました。学年に関係なく代表に選ばれたりすると、やっぱり嫉妬心を持つ人もいるわけです。いい気になっている、なんて言われたり、無視されたり嫌がらせをされたり…。
そういうときは、謙虚になることと同時に、こう言われました。「無視や嫌がらせもできないくらい、ダントツにうまくなってしまえばいい」と。ライバルと思わせないくらいうまくなる。そして、嫌がらせしてくるような子には、「しょうもないなコイツと思いなさい」と言うんです。
実際、私に嫌がらせしてもうまくなるわけではない。やるべきことは練習なんです。それがわかったら、『ホントにしょうもないなコイツ』と思いました。そうしたら、なんとも思わなくなった。こういうのも、大人の母の知恵でした。
 渡部:
渡部:
僕が戦場カメラマンの仕事ができているのも、妻の支えがあるからです。長い間お付き合いをして結婚したんですが、妻は幼少期に状勢が不安定な外国にずっと暮らしていたので、貧困や紛争の現場を自分の目で見ていて、“実情を世界の人々に届けたい”という戦場カメラマンの仕事をきちんと受け止めてくれました。世界で泣いている子どもたちの役に立てる仕事を妻が応援してくれているというのは、本当にありがたいことです。
でも、だからこそ、約束はキッチリ守ります。必ず消息を知らせることです。現場から、何度もしつこいほどに電話をかける、メールを打つ、直筆の手紙を書く。その約束を守り、アフガンやシリア、スーダンなどの前線に飛び込んでいきました。
僕の両親は、戦場カメラマンになることを伝えたとき、大反対でした。外国で何が起こるかわからない。万が一のことが起きたとき、悲しくて耐えられないと。だから、両親にも一定の期間の中で必ず写真を発表すること、現場から連絡を入れることを約束しました。
今は、取材をすること以上に危機管理を徹底しています。“安全最優先で動く。最前線で欲張らない。引く勇気を持つ”。家族と一緒だからこそ、仕事を続けることができていると思っています。
武田:
私は兄弟にも助けられているんです。兄が2人いるんですが、『美保がオリンピックに行ってくれるのがうれしい』とたくさん応援してくれました。夏はシーズンなので、練習のせいで家族旅行にも行けないんです。母がいつも私についてくれていたので、ずいぶん我慢もしてくれていたと思います。
渡部:
撮影で外国に行っていることが多いので、帰国して日本にいるときは、子どもにつきっきりで時間を使っていますね。一緒にお風呂に入ったり、食事に行ったり。いつも家族みんなで一緒にいることが大事だと思っています。家族こそ、僕の生活の基盤ですから。
戦場の厳しい環境で、食べ物も医薬品もない中、現地で暮らしている多くの人にとって、最後に生き延びていく力は、家族みんなが一緒にいることなんです。
限られたものを分け合い、気持ちを落ち着かせて生きていく。戦禍の一つ屋根の下にいると、家族を持っていることの喜びがいかに大きなものかがわかる。勇気や元気をもたらしてくれるものかがわかる。家族と一緒にいることは、僕にとっても一番の喜びです。
 武田:
武田:
昨年出産をして、今7カ月の男の子がいます。仕事をしながらも、母親が私にしてくれたように、きちんと子どもに向き合いたいです。悩みを持つような年頃になると、なかなか親には言えないことも増えてきますが、きちんと話し合い、子どものことを理解できる母親でありたいと思っています。
夫は目標と夢をしっかり持っている人ですから、同士という感じです。今は男女平等意識が高まっていますが、私は必ずしもそこにはこだわっていません。女の人にしかできないことがあるから。子育て中の授乳もそうですよね。
物質的な平等、時間的な平等より、大事なことがあると思っているんです。例えば、世界に羽ばたいて頑張ろうとする夫を応援して、一緒に喜びを分かち合うこと。そんな妻の役割があってもいいし、そういう考え方を持つ人がいてもいい。家族みんなの幸せのために、それぞれができることをする。そういう家族でいたいと思っています。
渡部:
講演はライブの真骨頂ですよね。戦場カメラマンの仕事はテレビや雑誌、新聞という媒体から、写真や原稿が視聴者や読者に届くわけですが、目や耳の感覚です。
講演の場合は、写真、声、言葉、身振り手振り、さらには僕の空気も伝わる。それこそ五感すべてで触れあうことができる。世界で起きていること、世界の子どもたちのこと、貧困や戦争のこと、伝えたいことを究極の形で伝えることができる。それこそ、戦場カメラマン冥利に尽きます。
武田:
アスリートを引退したとき、自分は何の役に立てるんだろうと思いました。でも講演でお話をさせていただくと、表情豊かに目をキラキラさせて真剣に耳を傾けてくださる方が大勢おられて、講演の仕事を続けたいと思うようになりました。
“言葉は力なり”だと本当に思います。シンクロで培った自分の体験を脚色なく伝えていきたいです。実際、小学校のときの思い出まで勝手に浮かんできて、身振り手振りで伝えている自分がいるんですよね(笑)。
聴講者の方がしっかりお話を聞いてくださるので、これまで頑張ってきたことがまた違った意味を持ち、他の人々に影響を与えていく。そして自分も元気になれる。悩みが小さく思えた、あきらめかけていたことをやっぱりやってみようと思った、なんて感想が聞けることもあって、私も本当にうれしいです。これからもたくさんの方々の人生に関われるような話をしていきたいと思っています。
取材・文:上阪徹 /写真:若松俊之 /編集:丑久保美妃
(2013年2月 株式会社ペルソン 無断転載禁止)


渡部陽一()
1972年9月1日、静岡県富士市生まれ。静岡県立富士高等学校 明治学院大学法学部卒業。戦争の悲劇とそこで生活する民の生きた声を体験し、世界の人々に伝えるジャーナリスト。 世界情勢の流れのその瞬間に現場…


武田美保()
アテネ五輪で、立花美哉さんとのデュエットで銀メダルを獲得。また、2001年の世界選手権では金メダルを獲得し、世界の頂点に。オリンピック三大会連続出場し、5つのメダルを獲得。夏季五輪において日本女子歴代…