目次
現在、テレビでお笑い芸人を見ない日はない。テレビ、ラジオ、映画、舞台など、さまざまな分野で幅広く活躍し、多くの若者が目指す人気の職業といえる。しかし今から30年前、芸能界でのお笑い芸人の地位は低く、まだまだ軽んじられていた存在だった。そんな逆境ともいえる状況から、お笑いをメジャーにするという理想に燃え、業界にさまざまな改革をもたらしたのが木村政雄さん。吉本興業時代は、80年代の「MANZAIブーム」を仕掛け、大阪が拠点だった同社の東京事務所を立ち上げて全国展開を成功させた。さらに本社に戻ってからは人気に陰りの見えた新喜劇を「新喜劇やめよっカナ!?キャンペーン」で見事に再生するなど、「お笑い」をビジネスとして成長させた立役者といえる。
2002年10月の独立後は講演・執筆活動、コメンテーターなど幅広い分野に活動の場を移す。2005年には50歳からのフリーマガジン「5L」(ファイブエル)を創刊し、編集長を務め、オンリーワンの活動をしている。
そんな木村氏の人生哲学、そしてターニングポイントとは……?
現場で出会った「やす・きよ」のマネージャーに志願
「吉本に入社した1年目は京都花月劇場の勤務です。団体のお客さんを入れたり、タレントさんに電話を取り次いだり、日報を書いたり。でも、1年もやれば同じことの繰り返しなんですね。もともと、クリエイティブな部門に関わりたかったので、人事課長に『替えてくれないなら辞めます』と電話したら、制作部に異動になりました。仕事は芸人さんのマネジメントや番組制作などですが、当時は“事務員”と見なされていました。“マネージャー”というのは、あくまで役者さんや歌手に付く人達を指すというのが芸能界の常識でしたので。実際、その頃の芸人さんたちは、テレビや営業の仕事が全部で1日に3件ぐらいしかありません。しかも、社員が現場のフォローをやっていなかった。芸人さんだけが行って仕事をしている状態だったんです。私は、それではアカンなぁと感じて、先輩に『芸人さんの仕事現場に行ってもいいですか?』と聞くと、勝手にしろと言われました。実際に行ってみたら、普段はマネージャーが来ないですから、芸人さん達が喜んでくれたんですね。若い私にグチとか、現場や会社の問題点とか、夢などを語ってくれました。その時に(横山)やすしさん、(西川)きよしさんと出会ったんです。
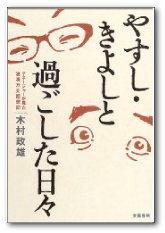
【やす・きよのマネージャー時代は、著書『やすし・きよしと過ごした日々』(文藝春秋)に詳しい】
お二人とは年代が近かったこともあって、自然と一緒にいる時間が長くなりました。それでこの際、自分がマネージャーになってスケジュール管理をしようと思ったんです。上司に直訴して志願しました。さっきも言ったようにお笑い業界では、マネージャーという呼び名がなかったんですが、勝手に『やす・きよ担当マネージャー』と言って、名刺まで作りました(笑)。やす・きよさんはコンビを組んですぐに上方漫才大賞の新人賞を取って、ちょうど有望株で売り出し中でしたね。ただ、私が付いてまもなく、やすしさんが不祥事(1970年12月、酒に酔ってタクシー運転手に対して傷害)を起こされた。やすしさんは2年以上の長期謹慎期間に入ったのですが、きよしさんはその間も相方を待つ、と仰ってくれた。人気商売ですから2年というのはお客さんに忘れられるには十分な時間です。厳しい状況でしたが、そうならないように奔走しました。やはり、私が今まで見た漫才で1番面白いのがやす・きよさんでしたから。もう1回、表舞台に立たせなきゃいけないという一心でしたね。ただ、結果的にあの一件がきっかけで、やす・きよさんとの距離はぐっと縮まったと思っています。あれがなかったら、人気コンビの後ろに付いているだけのマネージャーだったでしょうね。でも、あの不祥事で1回ゼロに戻ったので、本当の意味でもう出直して頑張っていきましょうと、同じスタート地点に立てたんです。そういう意味でよかったと今は思っています」
お笑いの地位向上の理想に燃えて―吉本の東京進出に賭けた想い
――やす・きよのマネージャーを8年以上勤めて離れた後、笑福亭仁鶴師匠などのマネージャーを経て、ついに東京吉本の立ち上げに参画する。今でこそ全国区の吉本興業だが、当時は拠点が大阪ゆえのハンディを抱えていた。そこで、白羽の矢が立ったのが、木村さん。しかし、立ち上げ当初のスタッフはたった2人だったという。
「そもそも、東京支社の立ち上げについては、会社から正式な辞令が出たわけじゃないんです。あるとき、林裕章(当時・専務)さんに、東京へ行こうかと誘われたからついていったら、『ここにしようか』と仰るわけです。私が『何がですか?』と聞くと、『東京に事務所作るねん』。『誰がやるんですか?』、『おまえや』って。そりゃビックリしましたよ(笑)。ただ、そういう会社って素敵だと思うんですね。だいたい企業の事業計画なんてウソばっかりじゃないですか。1年目の収支がどうとか、細かいことは一切言われませんでした。『赤字にはするなよ』ぐらいのものです。
当時は関西に会社の中枢が集中していましたから、「東京へ行く」イコール「左遷された」と皆には思われました。アイツは生意気だからやっぱり、みたいにね。でも、私はそれまでも何度も仕事で東京へは来ていましたから、感覚的にチャンスだと感じていました。最初は9坪の事務所に、スタッフは私も含めて2人。もう1人は当時、新入社員で研修中だった大崎君(※大崎洋氏…現・吉本興業の代表取締役社長)でした。東京には自分より偉い人はいませんから、もう東日本の仕事は全部ここが窓口や、と決めました。そうしろとは言われていませんでしたけど、勝手にそうしてしまいました(笑)。
最初は、在京のメディアや芸能事務所からは『大阪の田舎から来やがって』と見られていたかもしれません。でも、こちらには夢がありましたから。吉本を売りたい。有名にしたい。お笑いの地位を上げたい。それだけでした。誰だって、自分の仕事とか関わっている環境をメジャーにしていきたいじゃないですか。 それに、アメリカに行ってもコメディアンの地位はすごく高いんです。それなのに当時の日本では俳優さんや歌手のほうが高かった。悔しさがありましたね。だって、どちらにクリエイティビティが求められるかというと、私はお笑いのほうだと思うんですよ。自分でネタを考えて、表現する。脚本家も演出家もいないんですから。すべて要求される分野なのに、評価が低いのはおかしいでしょう。それに、稼げる世界にしないと若い人が目指しませんからね。ですから、お笑いの地位を上げたいなという思いはずっとありました。
ただ、吉本本社とはタレントのスケジュールをよく取り合いました。当時は劇場最優先の風潮がありましたから、どうしても一定期間はスケジュールを舞台に拘束されるんですね。でも、タレントにしたら東京のテレビ番組に出たらギャラはいいし、次の日からは騒いでもらえますからね。たとえば『笑っていいとも』に出たら、行きの飛行機と、帰りの飛行機で周りの反響が変わるほどです(笑)。舞台も大切ですが、時にはテレビのほうが芸人のためにもなる場合もあると思って、そこは本社とずいぶん戦いました」
大阪に戻れの辞令。吉本の“ 聖域 ”を構造改革
―――東京に「骨を埋めるつもり」で打ち込んできた東京事務所での日々。その成果によって、吉本のブランド、タレントの知名度は全国に浸透した。しかし、88年には本社に戻り、制作部次長を務めるようにとの辞令が届く。葛藤の末、「吉本新喜劇」再生プロジェクトの指揮を執ることになった木村さんは、ついに“タブー”に踏み込んだ大胆な改革を仕掛ける。
 「大阪本社に帰って来いといわれた時は悩みました。東京での業績は右肩上がり。私自身、テレビだけではなく、映画やレコードの仕事にも携わることができて非常に充実していた時だったんです。ですから、正直『それはないやろ』と思いましたね。ふと、大阪に帰らずに東京に残って、自分で何かを始めるかと考えもしました。でも、それと同時に、まだ吉本で完結していない気がしたんですね。結局、大阪に戻って実情がわかったんですが、劇場のお客さんが減ってきているので本社を建て直すという役目があったわけです。
「大阪本社に帰って来いといわれた時は悩みました。東京での業績は右肩上がり。私自身、テレビだけではなく、映画やレコードの仕事にも携わることができて非常に充実していた時だったんです。ですから、正直『それはないやろ』と思いましたね。ふと、大阪に帰らずに東京に残って、自分で何かを始めるかと考えもしました。でも、それと同時に、まだ吉本で完結していない気がしたんですね。結局、大阪に戻って実情がわかったんですが、劇場のお客さんが減ってきているので本社を建て直すという役目があったわけです。
今の吉本があるのは新喜劇のおかげです。でも、そのベースとなる観客動員力が落ちていた。実は新喜劇の芸人さん達もサラリーマン化していました。10~20分前に会場入りして、公演の合間に麻雀やって、終わったらスナックで飲んで帰る毎日。どう変えようかと考えていた時期に『劇団ふるさときゃらばん』(※全国各地を周ってミュージカルを上演するカンパニー)の公演を見て、これや!と思ったんです。飛びぬけたスターは誰もいないメンバーでも、舞台から熱いものを感じ、非常に魅力的だったんですね。
そこで打った手が『新喜劇やめよっカナ!?キャンペーン』でした。マスコミを巻き込んで、このままでは大阪から新喜劇がなくなるかもしれないと触れ込んだんです。もちろん賛否両論ありましたよ。でも、会社からは直接辞めろとは言われなかったですね。普通は上層部に直訴する人がいるんですよ。そういう干渉は一切なかった。その結果、新喜劇メンバーには良い意味での”危機感”が生まれ、世間も『新喜劇よ、頑張れ』というムードになったんです。よっしゃ、盛り上がってきたなという頃合で、新喜劇のメンバーと個人面談をしました。『大胆に変えようと思っています。これからは台本をベースにキャスティングしたい。だから台本によったら、ベテランの芸人さんでも通行人Aという芝居があるかもしれません。それでもやってくれますか』とね。あのまま旧態依然としたスターシステムで公演していたら、衰退していくのは目に見えていました。ですから、いくら芸歴が長かったり、ベテラン、スターと言われていても、変化に対応できなければ、生き残ってはいけない。こちらの方針に賛同して、それでも『やる』と答えてくれた人だけ残ってもらいました。
さらに劇場も構造改革を進めました。当時の新喜劇は10日単位で出し物を変えるという旧来のシステムでスケジュールが組まれていたんです。これは1週間単位で生活している一般のお客さんにはピンときません。毎週放映してくれるテレビ番組でも、10日単位ではズレが生じます。そこで、私は思い切って1週間単位の興行サイクルに変えました。それで今までよりスムーズに進行できるようになったんです 」
【ターニングポイント】何かを捨てなければ、新しいものは入ってこない
―――さまざまな改革をおこし、2002年10月には吉本興業を退職。常務取締役大阪本社代表にまで上り、周囲からは順風満帆に見えた輝かしいキャリアを、木村さんは自ら辞している。その真意とは何だったのか。
「やりたいことは全部やれたから、というのが辞めた理由ですね。吉本興業も“いい会社”になったんです。人気企業ランキングに入ったり、東大生が就職試験を受けに来たりね。ただ、『いい会社』と言われるようになったら、私の中では面白くないんですよ。もちろん、そうなってほしいから頑張ってきたのですが、何かつまらないと感じ始めたんですね。それなら、1回離れたほうがお互いのためにいいんじゃないかな、と。ひとりで『吉本やめよっカナ!?キャンペーン』です(笑)。それに、65歳ぐらいでどのみち辞めなきゃいけないわけです。その時になって何かを始めるのでは、体力が残ってなかったら辛い。それだったら、体力のあるうちにオイシイところで辞めたらいいかなと思いました。
 もともと、吉本で一生、というイメージはありませんでした。やす・きよさんのマネージャーを外された時も、東京から大阪に戻れと言われた時も辞めようかなと思っていましたから。ただ、当時はどこかやり残した感覚がありましたけど、今回は、これ以上、吉本をどうしていこうというイメージが持てなかったんです。会社の知名度を上げるとか、お笑いタレントの地位を上げるというメインテーマは叶いましたからね。あとは、その繰り返しになりかねません。
もともと、吉本で一生、というイメージはありませんでした。やす・きよさんのマネージャーを外された時も、東京から大阪に戻れと言われた時も辞めようかなと思っていましたから。ただ、当時はどこかやり残した感覚がありましたけど、今回は、これ以上、吉本をどうしていこうというイメージが持てなかったんです。会社の知名度を上げるとか、お笑いタレントの地位を上げるというメインテーマは叶いましたからね。あとは、その繰り返しになりかねません。
やはり、『上書き』を繰り返していても仕方がないと思うんです。それでは成長がない。例えば、吉本を辞めて自分のプロダクションやるのは、私にとっては進歩がないことでした。しょせんは昔の部下にお願いして、義理で発注されても、それが永遠に続くわけではありませんからね。どうせなら、それまでしてきたこととは全然違うところから発想していったほうがいいじゃないんだろうかと。そのためには1度、思い切った決断が必要でした。
誰にでも、キャパシティには限界があります。新しく何かを手に入れるためには、今ある何かを捨てなければ入ってきません。持っていたものを手離すと一瞬、不安になりますが、その代わりに新たに何かを得ようというパワーも生まれてきます。私も、辞めた後に何をする、というイメージはまったくなかったのですが、まずはとにかく自分の中にスペースを空けるために、『辞めること』を決意しました。その結果として今、吉本にいた時よりも自由に幅広く、新しいことにチャレンジできているのだと思います」
木村政雄からのメッセージ
「フリーになってから、老若男女、多種多彩な職業の方々とお仕事をさせて頂く機会があるのですが、お話をうかがっていて悩みが根深いなと感じるのは、60歳前後の方々なんですね。社会的には定年を迎えながらも、まだまだ力を持て余している世代なんです。それならば、この人たちを元気にしていくのが自分のテーマかなと思いました。この世代がどう生きていくかが日本の行方を左右すると思うんです。この人たちがつまらない生き方したら若者たちも未来に希望が持てないですからね。
そこで、彼らがワイワイ騒いで元気になれるコミュニティを作ろうと思い、この世代を称して『5L』(ファイブエル)という言葉を作りました。決して『団塊の世代』とか『シニア』とは言いません。だって、『団塊』って土くれとか塊という意味ですよ。『シニア』なんて、『死』が『ニア(near=近い)』ですからね(笑)。イメージが悪い。 さらに言うと、『5L』と書いて『5リットル』とも読めますよね。人生が10L(リットル)とするなら、まだまだ半分だという意味も含んでいます。
その『5L』世代向けに同名のフリーマガジンも創刊しました。編集長としてコラムを書いたり、インタビュアーをやったりと色々なことをしていますが、実は私はもともと新聞記者志望だったんです。就職試験で新聞社に落ちて仕方なく吉本へ入ったくらい(笑)。30年を経て、ようやく自分の夢が実現した気がしました。夢って、ずっと持ち続けていたら近い所まで行けるものなんだな、と思いましたね。ですから、もし今、仕事で一時的に思い通りにいかなかったとしても、それは『夢を預けておけるからいいことなんだ』と思った方が得です。うまくいかない状況に腐らずに、逆にラッキーなことなんだと発想転換することも大切です。
 キャリアとは、自分が歩いたあとにできる轍(わだち)です。皆それぞれ違う。ですから正解なんてありません。正しいかどうかは死ぬまでわからないんです。でも、お金や社会的地位があろうとなかろうと、本人が最期に『ああ、面白かった』と思えて死んでいけるなら、それは最高の人生なのではないでしょうか。自分で自分の人生をオモロイと思えるかどうか。そのためには、日々、何をすべきかがおのずと見えてくると思います。これから、私自身も、そう思える人生にしていきたいのと同時に、より多くの人々の人生を応援していきたいと思っています」
キャリアとは、自分が歩いたあとにできる轍(わだち)です。皆それぞれ違う。ですから正解なんてありません。正しいかどうかは死ぬまでわからないんです。でも、お金や社会的地位があろうとなかろうと、本人が最期に『ああ、面白かった』と思えて死んでいけるなら、それは最高の人生なのではないでしょうか。自分で自分の人生をオモロイと思えるかどうか。そのためには、日々、何をすべきかがおのずと見えてくると思います。これから、私自身も、そう思える人生にしていきたいのと同時に、より多くの人々の人生を応援していきたいと思っています」
(了)
取材・文:佐野 裕/編集・写真:上原 深音
(2009年8月 株式会社ペルソン 無断転載禁止)


木村政雄 きむらまさお
フリープロデューサー
夢に日付を入れよう。“夢を見続けられる”のも一種の才能である。(著書「五十代からは捨てて勝つ 自分株式会社をつくろう」より) 夢の実現に向け、2002年10月10日吉本興業株式会社退職後、フリー…
ターニングポイント|人気記事 TOP5

Vol.11 ファッションは人の生き様。 本当の“おしゃれ”は 生き方で決…
ドン小西

Vol.03 敵は己の中にあり。自分と向き合うことから逃げない
角田信朗

Vol.04 鉄板も舐め続ければ穴が開く。 積み重ねていれば転機は必要ない
室井佑月

Vol.08 明日に繋がる負け方をすれば、 勝ち続けることと同じなんですね
ますい志保

Vol.02 兄と比較されることで、自分の目標が明確になりました
荻原次晴
講演・セミナーの
ご相談は無料です。
業界25年、実績3万6700件の中で蓄積してきた
講演会のノウハウを丁寧にご案内いたします。
趣旨・目的、聴講対象者、希望講師や
講師のイメージなど、
お決まりの範囲で構いませんので、
お気軽にご連絡ください。






